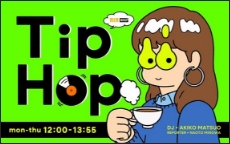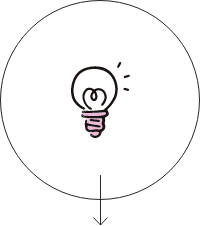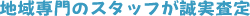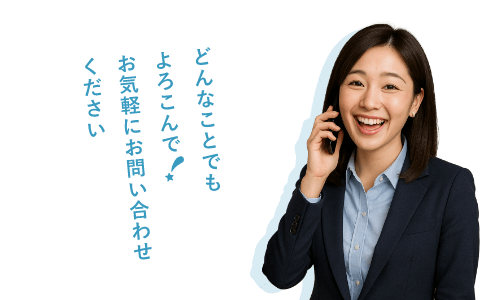2025.05.12
コラム時事情報
終活で後悔しない!居住用不動産の見極めポイント3選


こんにちは!人生の集大成を迎えるにあたって「住まい」の問題って本当に悩みどころですよね。持ち家を維持するべきか、賃貸に切り替えるべきか、はたまた老人ホームという選択肢も…。
実は、多くの方が終活で一番頭を悩ませるのがこの「不動産」の問題なんです。親から家を引き継いだけど維持費がかかりすぎる、将来のために今の家を売却すべきか迷っている…といった相談を日々受けています。
この記事では、終活における居住用不動産の選び方や見極め方について、失敗しないための10のポイントを徹底解説します!これを読めば「あの時こうしておけば良かった」という後悔を防げますよ。
不動産の専門家として培った経験をもとに、誰にでも分かりやすく、そして実践的なアドバイスをお届けします。ぜひ最後まで読んで、あなたの終活に役立ててくださいね!
1. 「持ち家、賃貸、老人ホーム?終活で迷ったときに知っておくべき不動産選びの極意」
終活において最も頭を悩ませるのが「住まい」の問題です。長年住み慣れた持ち家に住み続けるべきか、管理の手間が少ない賃貸に移るべきか、あるいは介護サービスが充実した老人ホームを選ぶべきか。この選択は将来の生活の質を大きく左右します。
まず大切なのは、自分の健康状態と将来の変化を冷静に見極めることです。現在元気でも、10年後、20年後の自分の体力や認知機能を考慮した住まい選びが必要です。階段の多い持ち家は年齢を重ねると負担になり、広すぎる住居は掃除や管理が困難になります。
持ち家派の方は、バリアフリーリフォームの可能性やコストを検討しましょう。手すりの設置や段差の解消、車いす対応のキッチンなど、最低限必要な改修費用は100万円から300万円程度が目安です。多くの自治体ではバリアフリー改修に補助金制度があります。
賃貸を検討する場合は、高齢者向け賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など選択肢が増えています。
老人ホームは、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホームなど種類が豊富です。入居一時金と月額費用の仕組みを理解し、万が一退去することになった場合の返金条件も確認しておくことが重要です。
どの選択をするにしても、立地条件は最優先事項です。医療機関へのアクセス、買い物の利便性、公共交通機関の充実度によって、生活の質が大きく変わります。特に徒歩圏内にスーパーマーケットや診療所があるかどうかは、将来の移動に不安がある方にとって決め手となります。
終活における住まい選びでは、「今」だけでなく「将来」を見据えた決断が求められます。感情だけでなく実用性を重視し、経済的負担と生活の質のバランスを考慮した選択をすることが、後悔のない終活への第一歩となるでしょう。
2. 「親が残した家、どうする?終活で絶対失敗しない不動産の扱い方3選」
親から受け継いだ家には思い出がたくさん詰まっていますが、同時に大きな責任も伴います。相続した不動産を最適に扱うことは終活の重要な課題です。この記事では、親が残した家をどう扱うべきか、後悔しないための10の選択肢とそのポイントを解説します。
①売却する:相続税の支払いや兄弟姉妹との公平な分割が必要な場合、売却は有効な手段です。不動産会社数社に査定を依頼し、最も条件の良い会社を選びましょう。
②賃貸に出す:安定した収入源として活用するなら賃貸がベスト。ただし、管理の手間や空室リスク、将来の修繕費用を考慮する必要があります。管理会社に委託すれば手間は軽減されますが、手数料が発生します。
③自分で住む:住み慣れた地域で暮らし続けたい場合は良い選択です。ただし、固定資産税や維持費、老朽化対策の資金計画は必須です。リフォーム費用も計算に入れましょう。
どの選択肢を取るにせよ、親の残した大切な財産を次の世代に適切につなぐためにも、早めの準備と情報収集が成功の鍵となります。
3. 「終活の盲点!居住用不動産で損しないための見極めテクニック大公開」
終活において居住用不動産の扱いは多くの方が頭を悩ませるポイントです。相続で思わぬトラブルを引き起こしたり、最悪の場合は大切な資産が大幅に目減りするケースも少なくありません。現役の不動産鑑定士によると、終活で不動産について検討する際に見落としがちな点があるといいます。今回は、居住用不動産を賢く見極めるためのテクニックを解説します。
まず重要なのが「将来の売却可能性」の見極めです。立地条件や建物の状態に加え、将来的な地域の人口動態も考慮しましょう。人口減少が著しい地域では、売却時に大幅な値下げを余儀なくされる場合があります。国土交通省の地価公示や都道府県地価調査などの公的データを活用して、地域の価格動向を確認することをおすすめします。
次に、リフォーム履歴や建物診断の結果を精査することが大切です。特に中古物件は、見た目の美しさだけでなく、構造上の問題や設備の寿命についても専門家の意見を求めるべきです。ホームインスペクション(住宅診断)を実施することで、隠れた問題点を事前に把握できます。
3つ目は「二次相続」を見据えた検討です。自分の相続だけでなく、配偶者が亡くなった後の相続も想定しておく必要があります。例えば、子供のいない夫婦の場合、配偶者が亡くなった後は、その親族(義理の親族)に不動産が相続される可能性もあります。このような状況を避けるためには、遺言書の作成や生前贈与など、計画的な対策が重要です。
また、固定資産税や都市計画税といった保有コストも見落とせません。相続した不動産を売却せずに保有し続ける場合、これらの税金は継続的に発生します。さらに、空き家になると管理費用もかかるため、トータルコストを計算した上で判断することが肝心です。
相続税評価額と実勢価格の差も把握しておくべきポイントです。不動産の相続税評価額は、一般的に市場価格より低く設定されています。土地は路線価、建物は固定資産税評価額をベースに計算されますが、実際に売却する際の価格とは乖離があることを理解しておきましょう。
資産価値が高い物件ほど、「共有」による問題も考慮すべきです。複数の相続人で不動産を共有すると、後々の売却や活用の際に全員の同意が必要となり、トラブルの元になりがちです。可能であれば、現金や他の資産と組み合わせて、不動産は一人の相続人が相続するような分割方法を検討することも一案です。
住宅ローンが残っている場合は、団体信用生命保険(団信)の加入状況も確認しましょう。団信に加入していれば、持ち主が亡くなった場合にローンは完済されますが、加入していない場合は、相続人がローンを引き継ぐか、不動産を売却してローンを返済する必要があります。
最後に、専門家のサポートを受けることの重要性を強調したいと思います。不動産、税務、法律の専門家に相談することで、後悔のない終活を進めることができます。
終活における居住用不動産の見極めは、決して一人で抱え込むべき問題ではありません。これらのポイントを参考に、ご自身の状況に合った最適な選択をしていただければと思います。
-
店舗へのお問い合わせ
- 0120-752-555
- 毎週水曜日定休
営業時間 9時〜18時
-
メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム
- こちらからご連絡ください
-
無料査定
- 無料査定
- 査定をご希望の方はこちら